
ブログとYouTubeで情報発信をしています。
ソーシャルワークやコーチングに関する基本的な知識、体系立てられた理論を紹介するだけではなく、実践に活用できるような形で情報をまとめています。
ソーシャルワーク・コーチングとは?
ソーシャルワークについては、2014年7月メルボルンにおける国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)総会及び国際ソーシャルワーク学校連盟(IASSW)総会において以下の定義が採択されています。
ソーシャルワーク専門職のグローバル定義
ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。
社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。
ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。
この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。
これだけではわかりにくいかと思いますので、少しだけ解説を付け加えますね。
私たち人間が、人生の中で「辛いな」「しんどいな」というような生きづらさを抱えることがあるかと思います。
ではその生きづらさについては「個人の責任」であり「辛いと感じる人が頑張ればいい」「その人に対してなんらかの介入をすれば解決する」ということばかりではありません。
なぜかというと、私たちは「社会」の中でいき、「環境」から大きな影響を受けるからです。
家にも学校にも居場所がないと感じるAさん
例えば、「家庭で辛い目に遭っている」「学校でも居場所を感じられない」というAさんいたとします。
ソーシャルワーカーはAさんの話に耳を傾け、今のAさんを取り巻く状況や、今後どうしたいのかということについて耳を傾けます。
そして、「家族関係の調整」や「学校に対する助言」を行ったり、「制度やサービスの活用」「支え合えるようなネットワークの構築」などを視野に、Aさんを取り巻く環境にもアプローチをしていくんです。
生活課題に取り組みウェルビーイングを高める
先ほど確認したソーシャルワーク専門職のグローバル定義には、
ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。
とあります。
Aさんが「生きづらさ」を抱えている時に、その課題を乗り越えて心身ともに健康で、社会生活をAさんらしく営むことができるよう「人々やさまざまな構造に働きかける」のがソーシャルワークです。
このケースだと、「Aさん自身」に働きかけるのはもちろんですが、それだけではありません。
「Aさんを取り巻く環境(家庭・学校)」「Aさんとサービスなどを結びつける」「ネットワークを開発していく」など、まさにさまざまな構造に働きかけをしていきますよね?
このように、
- 健康上の理由で仕事が続けられなくなり、生活が困窮するのではないかと不安を感じている人
- 家族の介護と育児で心身ともに疲弊して、助けて欲しいけど誰にも頼ることができないでいる人
などのケースでは、それぞれ「クライエント」の話に耳を傾け、その利益を追求し、幅広い視野で状況を見渡し、問題を構造的に整理し、介入の方向性を探っていくのがソーシャルワーカーです。
コーチング
ではコーチングとはなんなのでしょうか?
認知科学の理論やノウハウを駆使し、クライエントの自我(セルフイメージ)を書き換え、ゴールの世界にマインドを移行するアプローチを通じてクライエントの人生を幸せで豊かなものへとする実践。
セルフコーチング・パーソナルコーチング・組織コーチングなど、さまざまな形態を取りうる。
説明すると以上のような形になりますが、これも少しわかりにくいので説明を加えていきますね。
コーチングは、「クライエントの人生を豊かにすること」を目的として行われます。
コーチは、クライエントの話を聞きながら、問題の構造ではなく「認知」「認識」(心の動き・仕組みなど)に対して介入的な働きかけを行い、クライエントの可能性を解き放っていきます。
キャリアに行き詰まり不安を抱えるBさん
例えば、勤続10年の会社を辞めるかどうか悩んでいるBさんがいたとします。
Bさんはこれまで真面目にコツコツ働いてきましたが、会社の業績自体が良くない状態です。
今付き合っているパートナーとの今後などを考えたとき、経済的なことやキャリアそのものについてモヤモヤとして不安を抱えています。
このような状況があったとき、コーチはBさんのゴール設定からお手伝いします。
Bさんが今後、歩んでいきたいと思うキャリアはどのようなものか?
それを考える上で、「誰に対してどんな役割を果たしたいのか」「できるかどうかとか、過去や他者の評価にとらわれず、Bさんが本当に実現したい状態とは何か」ということを投げかけるなどして、Bさんがゴール設定できるようサポートします。
例えばそれが、子どもたちが地域でイキイキとした笑顔で、やってみたいことに挑戦できるような社会を作りたいと思い、それに対して自分は「遊べる場」「学べる場」「挑戦できる場」を作りたいと考えたとします。
それをゴールとした時に、今の会社にいることがゴールに近づくのか、それとも別の選択をした方がいいのかなど、考えることができるようになってきますよね?
また、ゴールは複数設定しバランスをとることで相乗効果を得ることができます。
例えば、「健康のこと」「家族とのこと」「経済的なこと」「地域や社会に対する貢献」「学び」など、複数のゴールを設定できるようサポートしていきます。
この時、ゴールはできるだけ壮大で、達成方法がイメージできないくらいのものを設定していくのですが、その時クライエントであるBさんは「不安」を感じたり「自分には無理」と思ってしまうことがあります。
こうして「現状に引き戻されそうになる」わけですが、ここでコーチは「あなたならできるよ!」という確信度(セルフエフィカシー)を高めるような働きかけを行います。
Bさんが不安や否定的な態度を取るのではなく「自分にはできる」という確信が持てるようにしていくんですね。
これが、コーチングです。
ソーシャルワーカー・コーチとして
これまで私は、ソーシャルワーカー・コーチとしての学びと実践を重ねてきました。
その経験を踏まえて、学んできたことをわかりやすくレクチャーしたり、実践の中で気づいたことをシェアしたりしているのが「ソーシャルワークコーチング」(以下のサイト)です。
このサイトでも、企画の案内などを行っていきます。


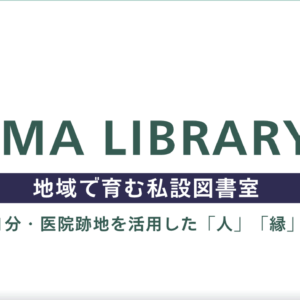

コメント